世界の状況と同期しながら、最新のテクノロジーとアートの結びつきを模索してきた初期の日本のアーティストたち。その実践の軌跡が、いかに現代に至る「批評」と「スペクタクル」という二つの方向性を生み出したか。キュレーターの山峰潤也が、日本のアート&テクノロジーが描いてきた歴史の道筋を独自の視点で論じたテクスト。オンラインメディアRight Click Saveとのコラボレーション記事。英語版はこちら(RIGHT CLICK SAVE)。
The RIGHT CLICK SAVE (English) version of the article is here.
*
日本は、20世紀後半テクノロジー分野が成長し経済発展を牽引することになったことは周知の事実である。そのため、国内外からみても「テクノロジー」が一つの日本のアイデンティティとなっていった。そのため、アートの分野でも、テクノロジーを活用したエンターテインメントやNFTアートといった領域で活躍するアーティストを多く輩出していくこととなる。しかし、その他方でこの分野における歴史的な流れについて、あまり知られていないのではないだろうか。
アート&テクノロジーの世界的な潮流の起点は、ロバート・ラウシェンバーグとベル電話研究所の所長だったビリー・クルーヴァーが1960年代に始めたExperimental in Art and Technologyであり、その活動の起点となった1966年のNYで開かれた「9 Evenings: Theatre and Engineering」とされることが多い。しかし、1950年代に瀧口修造を中心に、武満徹や湯浅丈二、山口勝弘ら十数名で結成された実験工房というグループがあったことが、日本のアート&テクノロジーの領域の前史的に存在していた。彼らはキネティック・アートやExperimental Film、パフォーミングアートの分野で活動した後、わずか数年でその活動を閉じていく。しかし、メンバーの多くは個々のアーティストとして1970年の大阪万博に参加していくこととなる。そして、主要メンバーの一人であった山口勝弘は、日本のメディアアートの先駆的存在として活躍し、岩井俊雄や明和電気など多くのメディアアーティストを輩出したまた筑波大学で教鞭を取るなど次の世代へと繋がる存在となっていった。
また他方では、1960年代には、アルゴリズムで描かれるコンピューターグラフィックが日本からも台頭していく。1968年にロンドンのICAで開かれた「サイバネティック・セレンディピティ」展やアメリカの月刊誌『Computers and Automation』の第6回コンピュータ・アート・コンテストで紹介されたCTG(Computer Technic Group)*、CG作品に加えコンピュータ音楽、人工知能研究まで至る多様な実験など1960年代からの活動を紹介する回顧展がZKMで開かれた川野洋が台頭していく。ジェネラティブアートと呼ばれるプログラミングによって生成されるアートの起点が、世界的にみても早く起こっていったことがみてとれる。

「Design 3-1. Data 4, 5, 6, 6, 6 [Design 1-4. Data 1, 2, 3, 3, 3]」 by Hiroshi Kawano / 1964 / Photography by Franz J. Wamhof. Courtesy ZKM Karlsruhe
こうしたメディアアートの萌芽からその後の発展へと繋がっていったのは、前述の大阪万博を始めとする巨大な産業イベントや、テクノロジーを基盤とする産業の発展が大きく関わっている。大阪万博は前述の通り、当時の若手アーティストが参画し、希望的未来をアピールする国家的プロジェクトの主要な位置付けをになっていく。また、大阪万博には前述のExperimental in Art and Technologyがペプシパヴィリオンを担い、アメリカ発のアートとテクノロジーの実験的な活動が紹介されることとなった。このペプシ館を霧で包む大規模なインスタレーションを実現することに尽力した中谷芙二子は、その後、EATと日本の接点を作っていくとともに、日本におけるビデオアートの先駆者の一人として活動し、またビデオを中心としたギャラリーやフェスティバルを企画していき、海外のアートを日本に紹介し、日本のビデオアートを世界に発信していく存在となっていく。
ビデオアートとその後に台頭してくるメディアアートは大きく結びついている。ビデオアートに関わるアーティストは、放送技術の発達が与えた社会の変化や、コンピューターの発達によってもたらされる情報化など、メディア環境への考察を深めていくと共に、新しい技術と表現の関係を実験していく領域となっていく。ビデオアートの始まりには、ソニーが60年代に発売したポータブルビデオカメラ「Portal Pack」が大きく関わっている。プロフェッショナルで高額な機材であったビデオが、このデバイスによって個人でも取り扱えるようになったことが鍵である。それは、テクノロジーが民主化されるようになることで個人が、マスメディアを中心とした権力構造に対するオルタナティブなメディアを作りだせる機会を作っていくことに寄与したのである。一方で、好奇心のあるアーティストたちが新しい装置を使って実験を重ねていくことで、開発者の想定を超えた使い方が見出されて新しい可能性が広がっていく点や新しい技術が生み出すスペクタクルをアピールしていくことに繋がっていった側面もあった。
日本のみならず、ビデオアートからメディアアートへと移行していく中でも、「技術革新が生み出すメディア環境への批評的な視点」と「新しい技術を使った実験を通してスペクタクルを生み出す」ことのそれぞれ異なる方向性の葛藤が大きく横たわっていくこととなる。日本においてはそれは、1985年につくばで開かれた科学博の中で発表されたRADICAL TVという映像チームと坂本龍一がコラボレーションした「TV WAR」に大きく反映されている。この作品では、テレビで映し出されてきた戦争シーンをサンプリングして、軍需技術によってより強大になる戦争という暴力とそれがテレビの中で広く消費されていく状況を表現する内容を持ちつつ、2000インチという当時世界最大規模のJumboTronというモニタをつかった一台スペクタクルとして表現された。そして、1980年代から90年代、00年代とテクノロジーとアートを横断するアーティストが次々と台頭していくこととなる。

「TV War」 by Ryuichi Sakamoto and Radical TV / 1985 / Courtesy of the artists
1980年代には、コンピューターグラフィックの学会であるSIGGRAPHで河口洋一郎と藤幡正樹という方向性の異なるアーティストが評価され、山口勝弘が教鞭をとった筑波大学からは岩井俊雄が登場し、後に多摩美術大学で教鞭をとることとなる三上晴子、鮮烈な映像や音響を用いたパフォーマンスで現代社会を照らし出すダムタイプなど、世界的に活躍するアーティストたちが台頭してくる。同時代には、ビデオアートの父であるNam June Paikが東京で大規模な展覧会を行い、この世代のアーティストを刺激していった。また、O美術館開館記念特別展 日本のCGアート展ARTS ON COMPUTERが開かれるなど、技術発展を基盤に経済発展した日本で、テクノロジーを用いたアートへの関心が高まっていく。
そして、90年代にはカメラや電子機器のメーカーであるキャノンが、新しい技術を使ったアーティストのプロジェクトを支援するキャノンアートラボ、ジェフリー・ショーの代表作「The Legible City」の世界プレミア公開を行った名古屋国際ビエンナーレARTEC(1989-1997/5回開催)、日本の最大手通信会社NTTによる日本初のメディアアートセンターInterCommunication Center[ICC]、90年台に始まった文化庁メディア芸術祭など、企業、地域行政、国などからメディアアートが注目されるようになっていった。また、こうした機運の高まりから、メディアアートを扱う大学が増えていき、新たな世代が台頭していくこととなる。
日本では、前述の筑波大学がメディアアーティストを輩出する先駆的な大学であったが、その後、三上晴子や久保田晃弘などが教鞭をとる多摩美術大学、プログラミングツールMAX/MSPの日本語の教科書を書いた赤松正行などが教鞭をとったIAMAS、藤幡正樹らが教えた東京芸術大学などで、多くの学生がメディアアートを学ぶようになっていった2000年代。ProcessingやArduino、openFrameworksなどの新しいプログラミング言語の登場とインターネットを通したオープンソースの概念が浸透していき、若い世代でもこの領域で学び、活躍していくようになる。しかし、作品を販売することが難しく、機材にも費用がかかるメディアアートを学んでも、大学の研究機関以外でその活動を継続していくことが難しいという現実があった。大学教員というポストは限られている一方、大学が増えればその分、卒業生が増えていくが、その受け皿がないという現実はアーティストの課題であった。こうした状況に対して、商業と結びつく形で突破口を開いていった存在が、リオ五輪の閉幕式の演出に参加し、高度なプロジェクションマッピング技術で知られるRizomaticsである。エンターテイメントやプロダクトなどと結びついた前例として、YAMAHAと電子楽器TENORI-ONを開発し、また多くの音楽ゲームを制作した岩井俊雄が、メディアアートという領域を越えて活動していった前例を踏まえ、真鍋大度を中心としたRaizomaticsが同世代移行のアーティストたちに生きる術を示していった。そして、同時期にウェブ関連会社であったTeamLabが参入してスペクタクルに溢れた没入型の映像インスタレーションで一般社会からの注目を集めていくことでメディアアートと呼ばれていた領域と産業が一気に結びついていくのである。しかし、そこには新しいテクノロジーがもたらす影響への批評的目線が、メディアアートという言葉から薄らいでいくことへの葛藤が、日本の同分野の人々の中でより深くなっていった時期でもある。
こうした状況の中で、ロンドンのRoyal College of Art(RCA)で学んだ福原志保や長谷川愛、スプツニ子らが日本にスペキュラティブデザインという概念を持ち込むこととなる。「起こりうる未来」を想像させ、テクノロジーのあり方や社会的バイアスなど顕にするこの分野は、バイオテクノロジーやジェンダー、AI、ロボティクスなどさまざまな領域と結びつき、アートのみならず広い分野からの注目を集めていくこととなる。そして、同時代の理工分野からは人間とロボットの境界を問うようなGeminoidがロボテックスの領域から生まれていった。
また最近では、身体的事情によって動けない人々が通信技術とロボテックスを通して働くことのできる環境を作り出したオリィ研究所や、AI技術を通して廃棄量を極力すくなくしたファッションプロダクトを提案するSynflaxなどが、資金調達を行いながら社会実装を行うビジネスと社会課題解決を同時に目指していく動きへの注目が集まっている。
そして、また別の角度では、NFTの登場により、80年代や90年代のアニメからインスピレーションを受けてギャルバースを作り出した草野絵美や、動物の絵で注目されたZombi Zooなどが登場し、コーディングカルチャーから生まれてきたジェネラティブアートという分野ではqubibiやGenerativeMasksの高尾俊介がクリプト関係者の中から注目されている。日本のアートシーンやマーケットの中では、まだこういった分野へのリテラシーが低く、国際的に取引されるダイナミズムがまだ浸透していっていないが、デジタルアートという世界に、売買可能性が生まれたことは新たな展開と言える。しかし、これらの動きは日本においてWeb 3.0という新たな時代を思わせる謳い文句と共に浮き足立ったままであり、この経済流動性が社会に還元されていくのか、という視点でより深く考えていく必要がある。
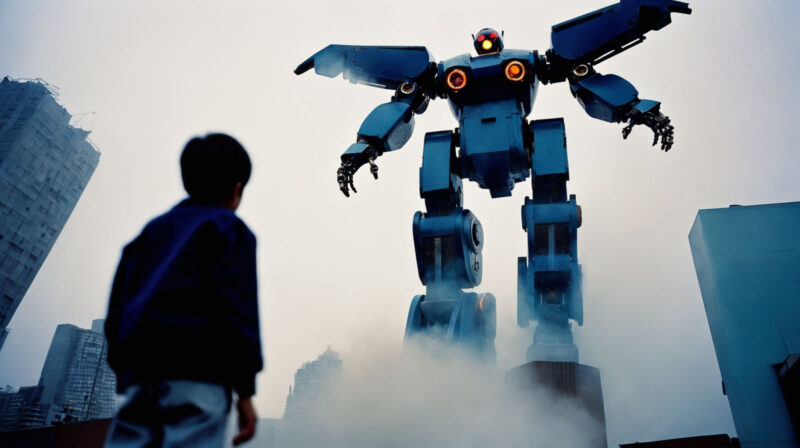
「Techno-Animism」 by Emi Kusano / 2023 / Courtesy of the artists
ここまでの時代変化の中で大きく言えることは、「技術革新が生み出すメディア環境への批評的な視点」と「新しい技術を使った実験を通してスペクタクルを生み出す」がコンフリクトしながら、芸術として社会への批評的な眼差しを芸術作品を通して示してきた時代から、経済流動性や社会実装というポイントを踏まえることを重要視する時代へと移行してきているということである。それは混沌の中にありながら、新しいパラダイムへの時代が動いてきていることの証明である。
- * CTG(コンピュータ・テクニック・グループ)は槌屋治紀と幸村真佐男の出会いをきっかけに、1966年12月に山中邦夫と柿崎純一郎を加えた4人(最終的に10名)で結成されたコンピュータ・アート集団。
