2月に水戸芸術館で行われた「ハロー・ワールド ポスト・ヒューマン時代に向けて」でのトークでエキソニモの赤岩やえが「Screenshot」というスライドを提示した。そのスライドでは順に、フルスクリーンかつツールバーを表示しないスクリーンショット、フルスクリーンでツールバーを表示したスクリーンショット、フルスクリーンを解除した状態のスクリーンショット、さらに、フルスクリーンを解除したディスプレイが映るようにカメラで撮影したもの、さらに、パソコンが置かれた状況がわかるように引いて撮影されたものが示された。スライドを見せながら、赤岩は最初はスクリーンショットというとウィンドウのコンテンツの部分だけを撮影したものだと考えいたが、実際にはブラウザのウィンドウを見ているし、さらにはデスクトップのウィンドウの重なりのなかでコンテンツを見ていることに気づいた。さらに言えば、ディスプレイのフレームも視界に入っているとすると、そこを含めて撮影されたものが「スクリーンショット」と呼ばれるべきなのではないかと考えるようになったと、赤岩は言っていた。赤岩が示した「どこまでをスクリーンショットと呼ぶか」という問題は、私たちとコンピュータとの関係を考えるきっかけを与えてくれるように思える。
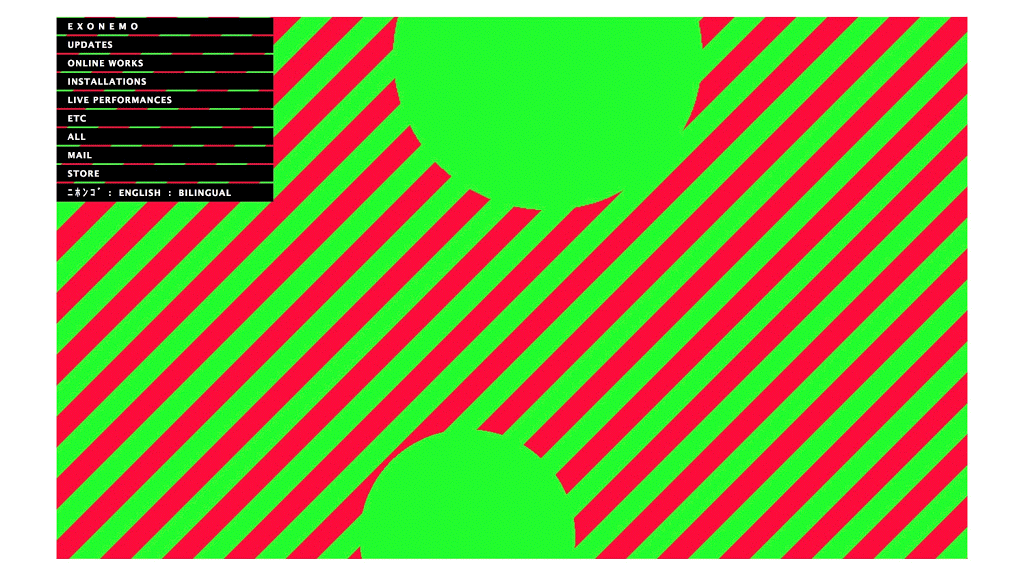
フルスクリーンかつツールバーを表示しないスクリーンショット、フルスクリーンでツールバーを表示したスクリーンショット、フルスクリーンを解除した状態のスクリーンショットまではハードウェアは介在しない。フルスクリーンを解除するとウィンドウの重なりが生まれて、画面に奥行きが生まれる。画面が「向こう側」に引っ込んでいくような感じがある。そして、ここまでのスクリーンショットにはハードウェアは写り込まない。「スクリーンショット」という名が示すようにどこかに撮影するカメラがあるとすると、カメラのレンズはディスプレイの向こう側にあり、こちら側に向けられていると考えられる。ここまでは、ディスプレイ手前には自分がいるような感じがある。私がそれらを操作できるような感じがある。
スクリーンショットが画面内で撮影されたときにコンピュータを操作する私がいると想定されていた場所で、誰かが実際にディスプレイを撮影するとき、勝手に想定される私と撮影した誰かが重ね合わされる。そして、私が弾き出されて、インターフェイスは前にあるのだが操作できない状態になる。インターフェイスから弾き出された私とディスプレイとのあいだに、あらたなサーフェイスを伴った空間ができる。ディスプレイ手前に現れた空間は可変的であり、私とディスプレイ上のイメージとをつなぐソフトウェア的な結びつきを引き離しながら、私そのものを含んで拡大していく。多くの場合、その拡大は部屋の壁という別のハードなサーフェイスで区切られることで終わる。ディスプレイの向こうの空間も壁というサーフェイスで終わる。ディスプレイがインターフェイスから離脱して、サーフェイスという別の状態で空間に存在している。しかし、それは距離を詰めればすぐにインターフェイスに戻る。
一度ソフトウェアから引き離されて、室内の一つのサーフェイスとなった画面からフルスクリーンかつツールバーを表示しないスクリーンショットへと遡って見ていくと、コンテンツのピクセルの集合のみが表示されたスクリーンショットもまた、操作可能性を消失したサーフェイスとして見れてくる。ディスプレイ、キーボード、マウスやトラックパッドといったハードウェアとのつながりを削除された純粋な画像として、ソフトなサーフェイスとなっている。引いた位置からハードウェアとともに撮影された「スクリーンショット」とコンテンツのみのスクリーンショットはともに、インターフェイスを構成するソフトウェアとハードウェアとの割合が崩れることによって、インターフェイス的な操作可能性を示さないサーフェイスとなっているといえる。
インターフェイスはソフトウェアが示す柔軟性を失い、ハードウェア的なサーフェイスとなったり、ハードウェア的な確かさを失いソフトウェア的なサーフェイスとなったりして、私との関係を失っていく。それでは、インターフェイスはいつからサーフェイスになるのか? コンピュータと向かい合っているときは、それはインターフェイスである。しかし、ノートブックのパソコンを開いたまま、遠ざかっていくと、いつしか、それが単なるサーフェイスになっていく。いや、いつまでもインターフェイスであることには変わりがない。しかし、それがコントロールできないような距離になったり、スクリーンショットになったりするときに、それは突如、サーフェイスになるのではないか。インターフェイスからサーフェイスへ、ここには私たちとコンピュータという「ハードウェアとソフトウェアとが一体化したあらたなモノ」との関係をアップデートするような何かがあると思う。
インターフェイスを経由した後のサーフェイスを追求していこうというのが、この連載の目標となるのだろう。それは、きっとクレメント・グリーンバーグが提起した絵画の二次元的な平面をアップデートするようなかたちで、ヒトとコンピュータとのインターフェイスを経由して現れつつあるサーフェイスを考えるものになると思われる。ヒトとコンピュータとのあいだでサーフェイスは一度インターフェイスとなり、表と裏とその透き間から成り立つ複雑なものとなった。この複雑さを考察したのが「モノとディスプレイとの重なり」であり、エクリでの連載「インターフェイスを読む」だったと言える。次は、インターフェイスが示す「表と裏とその透き間」という三つの要素をまとめて、シンプルに一つのサーフェイスとして見てみたいと思っている。表と裏という二つのサーフェイスとそのあいだの透き間という三つの要素を一つのサーフェイスとして扱って考えてみること。そこから何が見えてくるのか。「サーフェイスから透かし見る👓👀🤳」では、三つの存在からなるインターフェイスと一つのサーフェイスとのあいだを行き来しながら、アートに限定されることなくいろいろと考えていきたい。
水野勝仁
甲南女子大学文学部メディア表現学科准教授。メディアアートやネット上の表現を考察しながら「インターネット・リアリティ」を探求。また「ヒトとコンピュータの共進化」という観点からインターフェイス研究を行う。